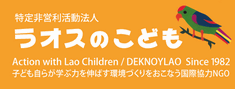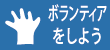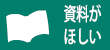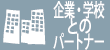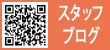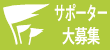これまでに実施したプロジェクトの報告
近年実施した読書推進プロジェクトを報告します。
※クリックすると報告のページが見られます
■ビエンチャン県における中学校の図書館整備を通した読書推進事業
2019年3月〜2022年7月
■学校図書室の地域への展開事業
2014年2月〜2018年1月
■小中学校における図書活用強化事業
2011年10月〜2013年10月
■読書推進運動の自立的運営の定着化事業
2010年3月〜2012年1月
■図書箱・図書袋配付プロジェクト
1992年〜2012年
■ラオスのこども40年のあゆみ