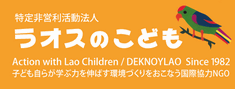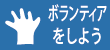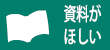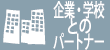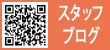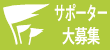「子どもに本を届ける」
読書推進プロジェクト

1992年、ラオスで最初の本を出版したときに驚かされたのが、ラオスには本の流通システムがない、ということでした。出版した本を子どもたちに届けるには、手渡すしかなかったのです。
現在でも、ラオスには本屋さんは数えるほどしかありません。一般の人が読む本は、市場の文具売り場の片隅で細々と売られているのが普通です。このような状況から、「ラオスのこども」は、全国の子どもたちに本を届けるために、読書推進活動として「図書配布プロジェクト」と「学校図書室プロジェクト」を展開し、書店もなく、子どもたちが本に触れる機会のないラオスで、小学校などを通じて子どもと本の出会いを広げてきました。
図書配付プロジェクト
読書との出会いから子どもたちの大きな夢が広げるため、ラオス国立図書館の「読書推進運動」に協力し、1992年から子どもたちに本を届けています。2012年6月末までに小中学校を中心に全国2,721校へ図書セットを配付しました。また、累計2,234校をフォローアップしました。 ※図書箱・図書袋については「これまでに実施したプロジェクト」参照
学校図書室プロジェクト
 より日常的に、継続的に多くの児童生徒が読書に親しむことができるように、空き教室に本棚などの備品と本をそろえ、運営方法や読書のすすめ方などを伝えて、学校に図書室を作る活動です。支援の図書室は、親しみを込め、ハックアーン(Hak
Arn=ラオス語で「愛読」の意味)という愛称をつけられており、2022年6月末まで349ヶ所の開設支援を行いました。
より日常的に、継続的に多くの児童生徒が読書に親しむことができるように、空き教室に本棚などの備品と本をそろえ、運営方法や読書のすすめ方などを伝えて、学校に図書室を作る活動です。支援の図書室は、親しみを込め、ハックアーン(Hak
Arn=ラオス語で「愛読」の意味)という愛称をつけられており、2022年6月末まで349ヶ所の開設支援を行いました。
学校図書室は、次の手順で開設されます。
- 以下の基準により選定した学校に、新たに学校図書室を開設します。
- 図書室として利用できる空教室がある(既存の設備を改修して利用し、新規建築等は行わない)
- 図書室担当教員を複数決め、責任をもって図書室管理ができる状態にする(選任である必要はない)
- 開設後、地域住民にも広く図書室を開放する
- 教育局スタッフが学校を訪問し、状況確認をしている
- 当会スタッフおよび国立図書館スタッフを派遣し、図書室開設の指導を行います。図書室開設式には、全教員および生徒や地域住民の代表にも参加を促し、地域全体で利用してもらうよう働きかけます。式典後には、図書室運営・管理方法や、読み聞かせやゲームなど、
 子どもたちを本に惹きつける手法に関する研修を行ないます。図書室入口に、支援者名を記載した「看板」を設置します。
子どもたちを本に惹きつける手法に関する研修を行ないます。図書室入口に、支援者名を記載した「看板」を設置します。 - また、開設後も新しい図書の補充を行います(原則として、開設後3年間継続)。
読書推進セミナー
ラオス語図書が配布されても、先生自身が本の活用や管理を知らなければ、子どもたちに本の素晴らしさが伝わりません。(教師自身が子どもの頃に本を読んだことがなかったということもしばしば…)。そこで、学校の先生たちを対象にセミナーを開催。講義と実技を織り交ぜて指導します。